「年収は上がったのに、手取りが増えない…」そんなモヤモヤを感じたことはありませんか?
実はその原因、「課税所得」がカギを握っています。
課税所得をうまくコントロールすれば、払う税金を減らせて、その分手元に残るお金を増やすことができるんです。
この記事では、家計の味方・FP3級有資格者のともが、課税所得の仕組みと減らし方を、税金の知識がない方でもスッと理解できるようにやさしく解説します。
「なるほど、こうすれば手取りが増えるのか!」と実感できる内容になっているので、ぜひ最後まで読んで、これからの生活に役立ててくださいね。

この記事では課税所得の仕組みや減額する方法をわかりやすく解説しています
税金はよく分からないし興味もないという人向けにわかりやすく解説し以下のことを学べます。
- 課税所得とは税金の利率がかけられる数字のこと
- 課税所得を減らす方法
知識を身につけて、お金の心配をなくす未来をコツコツ築いていきましょう。
課税所得とは税金の利率をかける最終の数字

課税所得の定義
年収から費用や控除を差し引いて残った金額に税率かける、この残った金額を課税所得といいます。
課税所得の算出をわかりやすくした式です。
なぜ計算して課税所得を出すのか、それは年収に直接税率をかけると税負担が大きくなります。
それを防ぐため課税所得という制度が用意されました。
年収別税引後手取り概算表
下の表は対策していない場合の税金の金額、手取りを概算で計算した早見表です。
| 年収 | 税金(社会保険料込) | 手取り |
| 200万 | 37万 | 163万 |
| 300万 | 65万 | 235万 |
| 400万 | 93万 | 306万 |
| 500万 | 125万 | 374万 |
| 600万 | 163万 | 436万 |
| 700万 | 203万 | 496万 |
※以下の条件をもとに概算で計算しています
- 40歳未満(=介護保険料なし)
- 夫婦と子ども1人の家族構成
- 賞与は含まず、年収を12等分した月給で概算
- 社会保険料、所得税、住民税すべて含む
収入の約20%が税金で差し引かれる計算になります。

所得税・住民税の利率が課税所得にかけられる

課税所得にかけられる所得税、住民税の税率表です。
どのくらい税金がかけられるかをチェックしてみましょう。
所得税・住民税早見表
| 課税所得金額 | 所得税率 | 住民税率 | 合計税率 |
|---|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% 低 | 10% | 15% |
| 195万円超え~330万円以下 | 10% 低 | 10% | 20% |
| 330万円超え~695万円以下 | 20% 中 | 10% | 30% |
| 695万円超え~900万円以下 | 23% 中 | 10% | 33% |
| 900万円超え~1800万円以下 | 33% 高 | 10% | 43% |
| 1800万超え~4000万円以下 | 40% 高 | 10% | 50% |
| 4000万円超 | 45% 最高 | 10% | 55% |
所得税は年収が上がるほど税率が高くなります。特に330万円、900万円を超えると税率が大幅にアップ!
💰 社会保険料も含めると収入の約20%が税金として差し引かれる
住民税は一律10%ですが、所得税は累進課税といい年収が上がるほど高くなり、特に年収が330万円、900万円を超える時は10%も上がります。
そこに社会保険料も加わり収入の約20%が税金として給与から差し引かれるので年収が上がっても手取りが増えたという実感がないのはこの税金が大きな影響を与えています。

控除を使い課税所得を減らす
控除とは税金を減らせる制度
控除をわかりやすく言い換えると「各家庭で経済的な事情はさまざまなので、税金を減額する制度をいろいろ用意しているから該当する人は活用して課税所得を減らしてね」ということです。
イメージしやすいように具体例を出して説明します。

控除の具体的イメージ
子供のお小遣いに”お小遣い税”という架空の税金があったとして、毎月お小遣いを1000円もらえると仮定します。
しかしこのお小遣いには10%の”お小遣い税”がかかります
1000円 x 10% = 100円
しかし、この税金には特別なルールがあります
お手伝いをがんばった子はその仕事内容に応じて上限500円分を税金計算から外してもいい特別ルールが
あります。
お手伝いをしっかり頑張り、上限500円差し引かれたとして
(1000円 – 500円) x 10% = 50円
課税所得が控除を使用することで半分に減少しました。
500円分を税金の計算から外した、この特別ルールが控除というわけです。
上の例えを図解にしたものです。
各家庭で経済的な事情はさまざまなので、税金を減額する制度をいろいろ用意しています。
該当する人は活用して課税所得を減らしましょう!
📊 控除なしの場合
🎁 控除ありの場合
• 生命保険料控除
• 地震保険控除
• ふるさと納税
• 住宅ローン控除(最大21万円)
控除額分だけ課税所得が減る → 税金が安くなる → 手取りが増える!
知識があれば選択肢が増えて、自分の資産を守ることができます。
控除をどう使えば課税所得を減らせるのか
サラリーマンが使うことの多い控除は下記になります。
- 配偶者控除
- 生命保険料控除
- 地震保険控除
上で紹介した控除は年末調整時期に指定書式の入力や必要書類を提出すれば、
会社側で確定申告を実施してくれます。指定書式や書類は企業によってそれぞれです。
次に紹介する控除は自分で確定申告をする必要があります。
- 医療費控除
- ふるさと納税
- 住宅ローン控除(初年度のみ確定申告が必要)
ふるさと納税は自治体5つまでであればワンストップ特例を申請し、必要書類を提出すれば確定申告は
不要です。

控除額の一例
- 配偶者控除→上限38万円
- 医療費控除→上限200万円
- 住宅ローン控除→21万円 ※新築、年末残高3000万円で計算
控除を受けるには一定の要件があります。各控除の説明や要件はこちらをご覧ください。
課税所得を減らせれば家計に余裕を生み出せる
課税所得は控除を使い減らす、減らした分だけ手元の現金が多く残せるという仕組を図解で簡単に復習します。
寄付金控除の一種で、税金を減らしながら返
身近に感じる控除の一つにふるさと納税があります。
これも寄付金控除という控除で、返礼品までもらえるとても嬉しい控除ですね。
ふるさと納税は現時点ではお得な控除ですが、これも知らなければ恩恵は受け取れません。
お金の知識というのは知らないことで損をしてしまう怖さがあります。
逆に知ってさえいれば数ある選択肢を使い自分の資産を守ることができます。
みなさんのお金の知識が1つでも増えて、選択肢が増やせるようにこれからも分かりやすい
解説をしていきます。
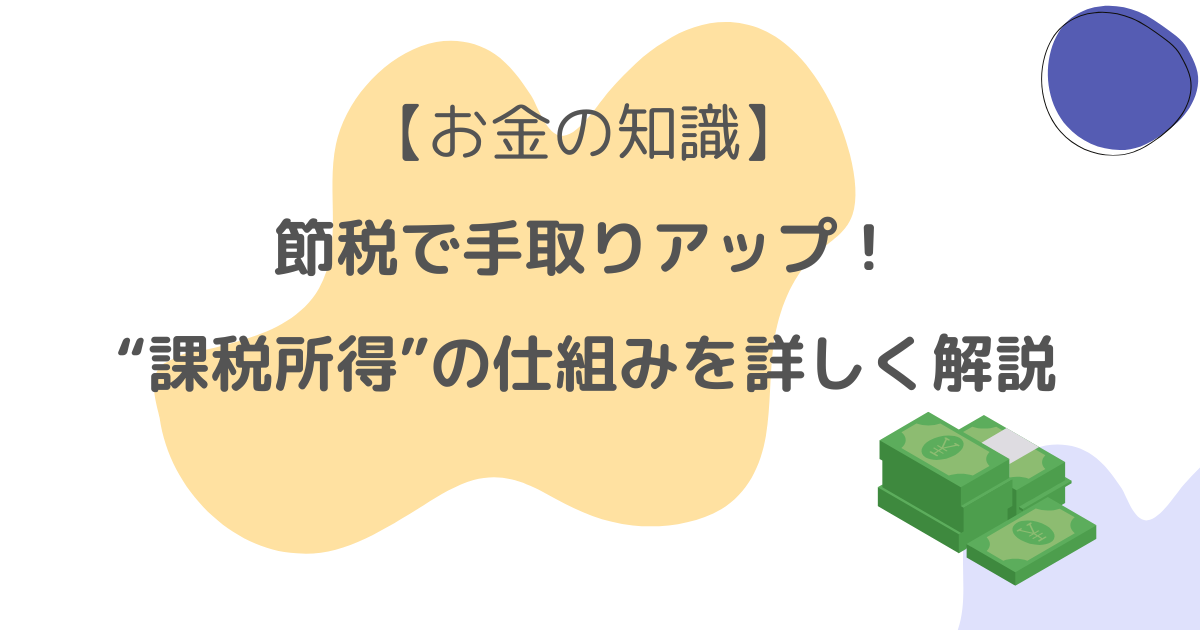
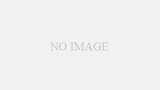
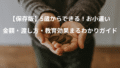
コメント